
1.ポスト・インターネット・アート (Post-Internet Art)
2018年6月2日に初台のICCで始まった「オープン・スペース 2018」は、メディア・アートにおける今日的な表現の数々を様々なパースペクティヴから紹介する毎年恒例の展覧会となっている。第13回目となった今回は副題に「イン・トランジション」を掲げ、今日のメディア・アートのデフォルトとなりつつあるテクノロジーの現在を移行期と捉える狙いが伺える。
筆者はそこでいくつかの作品をピックアップしながら、この「イン・トランジション」が意味するところをテクノロジーの状況はもちろんのこと、そのトレンドの一角を成す環境的・制度的な移り変わりとも思われる現象についても触れてみたいと考えている。
はじめに環境的な現象について述べるとすれば、今回の展覧会にセレクトされているメディア・アート作品のかなりの割合を占めるものの体験方法やユーザビリティが、世界のあらゆる市場に普及した商業的かつ一般的な設定を受け入れる形で、表現の基礎と据えられていることが挙げられる。
これらの作品はGoogleのサーチエンジンやGoogle Mapのデータを素材としたり、AppleのmacOSを所与の起動環境として利用したりして、こうしたツールが現代に広く浸透していることを前提としつつ、メディア・アートとしては、アーティストがいかにそうした環境をハッキングするあるいはアプロプリエーションするかに美的・批評的プレゼンテーションの行方が委ねられている。
例えば、永田康祐による《Sierra》(2017年)では、会場に設置された平凡なPCの画面上に、macOSの現在のバージョンSierraが映し出され、字幕によって北米のシエラ・ネバダ山系にまつわる西部開拓史の逸話が紹介される仕組みになっている。鑑賞者はデスク・トップ上で関連動画のリンクへ飛んだりGoogle ストリートビューの履歴を探ったりすることもできる。

永田康祐《Sierra》(2017)©︎ NTT ICC
Apple社では、以前はOS Xのバージョンの名称をパンサー、タイガー、レパード、ライオンなどネコ科の動物を採用していたが、ここ数年は社の拠点のあるカリフォルニア州のサーフィンの名所やヨセミテ国立公園のクライマーのメッカ、そして現在はSierra、次にはMojave砂漠が予定されている。こうした名称はいまや私たちにとって常に更新されてゆくOS Xのバージョンを示す空っぽな単語に成り下がってしまうところを、アーティストはその固有名に元来含まれていた歴史的アーカイヴを呼び戻し、私たちにコンピュータ端末の物質性とOSのバージョンの系譜、そしてそれらがいかにツールの使用目的に置き換えられ透明化してゆくかを批評的に表現している。
同じように批評的な作品としては、ジェームズ・ブライドル《オートノマス・トラップ 001》(2017年)と、新進アーティスト紹介コーナー「エマージェンシーズ!034」で発表されている柴田真歩《XNN (X News Network)》(2018年)の二つを挙げることができる。

James Bridle《Autonomous Trap 001》(2017)©︎ NTT ICC
前者は、AIに学習させるための視覚的言語やインターネットの情報が爆発的に物理世界に偏在しつつある現象をNew Aestheticと呼び、旧来のマルクス的唯物史観におなじみの、AIや機械による人間の労働力の補完・拡張が生産関係を向上させるという議論から離れ、もはやAIや機械は人間を仲介し補助するどころか置き換えていくという、未来についての警鐘を鳴らすような内容を発信している。※
つまり私たちの近くで機能しているはずの金融システム、ビッグデータにより編集されるターゲット・マーケティング、そしてオンライン・ショッピングのポイントやお得なセール情報に至るまで、私たちがコントロールしていると信じて疑わない日常の情報端末ですら、私たち消費者は気づかないところで、そのアルゴリズムによって誘導され支配されている。メディアはソフトウェアが紡ぎ出す確証のないニュースに満ち溢れていて、どのように社会が統制されているのか見当がつかなくなってきている。
そこでブライドルは社会に導入されつつある自動運転システムに注目し、実線は進入不可、破線は進入可能というAIの視覚的判断をハッキングする形で自動運転システムを作動不能な状態に追い込む様子を映像作品として発表している。さて、ブライドルは市販のものではなく自ら自動運転システムを開発し実装しているわけだが、そこには急激に発展するAIが次々と私たちの支配から逃れながら社会に浸透し、私たちが世界と渡り合う方法がすでにこうした新しいテクノロジーやツールの発達に追随する形で更新されていることを踏まえ、私たちは常にこうした状況について理解することを努力すべしというアドバイスが込められている。
続いて柴田真歩の《XNN (X News Network)》についても、私たちが日頃当たり前のように受け入れているニュースの信憑性を考察させる契機を生み出している。アーティストは、様々なニュースの実写の映像をロトスコープによってクレヨンで描いた輪郭線へと簡略化し、アナウンサーが発するセンテンスを単語毎に分断してプログラムによって文法的に通じるように再構成することで、現実にはなかったニュースがあたかも存在したかのように錯覚させている。

柴田真歩《XNN (X News Network)》(2018)©︎ NTT ICC
ICCが展覧会の特設ページで公開しているインタビューによると、柴田は実際に何かあったことは分かるが何があったことかは分からないという違和感を以前より抱いており、例えば中古レコードを蒐集する際、盤面についた傷を目にしても以前のオーナーのことは知るよしもないという事実にインスパイアされることがあるという。
ここには明らかに、単にメディアやテクノロジーの性格的な部分に対するリベラルなスタンスが指し示されているだけではなく、アートにとって重大なフェティシズムの領域がにじみ出ていると考えられる。詳しくは、次のチャプターとして予定している「制度的」なイン・トランジションにて触れるつもりだが、いずれにせよ、アーティストは物質と記憶や情報といったハードとソフトの間に生じる違和感にインスパイアされ表現のきっかけにしているようだ。だが、もはやメディア・アートの形式の一つに数えられるポスト・インターネット・アートの表現手法に糸口を見出していることは、少し性急な判断だったかもしれない。
少し前のメディア・アートであれば、大友良英やクリスチャン・マークレーのように、以前使われていたプレイヤーとレコードをそのまま表現に使う表現が主流だっただろうし、テクノロジーの現在への反省的なメッセージを込めるのであれば、これまで扱ってきた数作品に顕著なOSやインターネット環境のナイーヴなまでの容認を基礎とする表現に行き着くことは否めない。
その路線で言えば、「環境的」移行期では、アーティストはガジェットや装置といったフィジカルな物質に直接関与して連結や接続といった操作で何らかのアクションを引き起こす場—-つまりハードウェア・インスタレーション—-から、ソフトウェアの一般的環境を前提としたプログラミング表現—-つまりソフトウェア・デモンストレーション—-へ移行していると言えないだろうか。
次に徳井直生+Qosmo《Imaginary Soundscape》(2018年)を取り上げてみたい。このユニットはネット上のアーカイヴやビッグデータの素材をニューラルネットを駆使したアルゴリズムによって再構築し、批評的でありながら、極めて美的なプレゼンテーションを行うことに定評がある。今回も例に漏れず、徳井とQosmoは独自のAIを用いてGoogleストリートビューの大量の画像データを解析し、分類し、そして三面の壁に投影し、実際には存在しないがありそうな風景を描き出している。さらに画像の上には大量の動画からニューラルネットが風景と合致すると判断しセレクトした音源が貼られ、視覚的にも聴覚的にも想像上の風景が誕生している。

徳井直生+Qosmo《Imaginary Soundscape》(2018)筆者撮影
徳井らの意図するのは、三面の壁に投影される架空の風景が、アルゴリズムが選択した組み合わせによっては繁華街とスラム街が並列されたり、自然風景と人工物が同時に映し出されたりと、社会に潜む様々な問題を連想させるコンビネーションもありうるという開けたスタンスであり、二人はそれを総合的に風景画と呼んでいる。
実際に作品を観てみる。北米のラストベルトにある小さな工場の町なのだろうか、どこにでもありそうな田舎の寂れた市街地の様子に見える。サウンドは風切り音や草木が擦れるような自然音で満たされていて、寂寥とした雰囲気だ。こうした状況は、1960年代にフーコーが述べた「ヘテロトピア」の概念を彷彿とさせる。
数多くの断片的な可能世界からなるひとつの不可能な空間における共在であり、本来ならば相容れず、相容れるはずもないような複数の空間がひと所に並置されるようなトポス・・・このことをフーコーはユートピアの手がかりの一つとしてヘテロトピアと呼んだと考えられ、リアルではないが可能的な世界が、それが可能的であるゆえにアクチュアリティを持ちうることを示唆していた。
ただし、可能的であることを可能的であると認識するのは、個別的な判断に委ねられることは明らかであろう。繰り返しになるが、本作で壁に投影されている画像と音声のセレクションとコンビネーションはAIによって恣意的に導き出されているため、可能的ではあるが、一般的理解や想像力を掻き立てるような固有的な決定打を持つことができない。すると、本作は明確なメッセージを発信する社会派のアートと異なり、視聴者のほうに備わった視覚的経験やニュースなど社会問題への知識にある程度触れていないと状況を想像することすら困難であることは否めない。単なる冷たい画像としてストリート・ビューから採集された素材は、写真のインデックス的性格に染められ、そこで何かあったことは分かるが、それがいつであったのか、そして、それが何であるかは分からない、あるいは分かるとすれば文脈や受け手に委ねられることになるという宙吊りの有り様だけを伝えている。
このように物語性の伝達が受け手次第であるということは、作家が展覧会のHPのアーティスト・ステートメントで説明する思惑とは異なり、作品が訴えるべき明白なトラウマとは、そこには一切のトラウマがないということになのである。もちろんそのことが、ユートピア/ディストピアの表裏一体性を暴き出す重要な手がかりであることは、作品自体の強度が充分表現できているだろう。徳井らの卓越した創造性は、ネット上に氾濫した過去のデータをいかようにも分析・編集するアルゴリズムの開発能力にある。
以上に挙げた他の作品との関係へと飛躍的に考えてみれば、こうした「環境的」移行期にあるメディア・アートは、現在のテクノロジーや一般的ツールを批評的な眼差しで見透かすために、AppleやGoogleが蓄積してきた情報のアーカイヴを素材として用いながらも、独自の優れたアルゴリズムやシステムの開発と運用など、ソフト面を基礎とした「クール」な表現であると言えるだろう。たしかにこれらは一般的にアクセス可能な情報を操作するため反省的かつ批評的な表現には極めて適してはいる。だが単なるデータとしてフラットにされた非・歴史的な情報が現在進行中の1秒1秒のタイムフレーム上に再構築されているため、全体を俯瞰することができずメッセージの伝達力が弱いだけでなく、同時にメディア・アートらしい目新しさや独創性とは少し離れたところに追いやられがちであると言えなくもない。
だが、そこには一切の後ろめたさはない。なぜなら、こうした反省的な表現は、100年前にマレーヴィチがシュプレマティズムで実行していた本来の意味のアヴァンギャルド、前-衛、つまり「先に立ってガードする」ことに近しい目論見だと考えられるからだ。ロシア・アヴャンギャルドの前衛は、決して同時期のキュビスムやフォーヴィスムのようなラディカルな絵画表現へのカウンターとしてのプログレッシブで革新的な運動ではなく、マニフェストは存在しないものの、その本質は、次々と台頭してくる近代テクノロジーを前にして一息つき、テクノロジーと人間の関係性を正しい方向に歩ませるための美学的考察を提案するものであったことを思い出しておきたい。
2. 抽象化装置(Abstraction Apparatus)
続いて、今度は「イン・トランジション」に垣間見えるメディア・アートの制度的な移行期について考えてみることにしよう。
本展覧会では、以前にも増してVRやARを駆使した作品が多く見られる。こうしたテクノロジーの近年のめざましい発展と普及を鑑みれば当然である。統計を専門とするStatista社の情報によれば、2018年はまだ半ばだというのに世界で500万ユニットが販売されてきたという。2017年は一年間で400万ユニット足らずだったことを考えると、間違いなく伸びている。メーカーはSONY、Oculus(Facebook)、HTC、マイクロソフトが主流ではあるが、新規参入するメーカーも数社あることから注目されている市場であることは間違いないだろう。
さて作品を見てみよう。ライゾマティクスリサーチ《リカーシヴ・リフレクション》(2018年)は、モーション・キャプチャによる映像とサウンドを合わせた映像作品といえばシンプルに聞こえるが、はたして中身は複雑だ。まず目の前には視覚的な装飾がミニマルな奥行きのある空間が映し出されていて、音楽が流れている。鑑賞者が画面の前に立つと、その骨格がフレームとなって画面にリアルタイムに表示されるのだが、同時に、その周りに別のグループのフレームの身体が鑑賞者の動きと連携してダンスをし始める。作品の説明によれば鑑賞者の身体はマイクロソフトの市販のモーション・キャプチャ装置「Kinetic」を用いてサンプリングされ、よくライゾマティクスとコラボレーションを共にしているダンス・カンパニーELEVENPLAYのダンスデータを学習したモデルをサンプリングしたデータと合わせて、少し先を予想しながら映像として投影しているという。

Rhizomatiks Research《リカーシヴ・リフレクション》(2018) 筆者撮影

Rhizomatiks Research《リカーシヴ・リフレクション》(2018) 筆者撮影
そこでは、三次元の身体のボリュームの把捉、モーションの解析、モーションの緻密なデータ化、リアルタイムで再録したデータと過去のダンスデータをハンドリングするスピーディな機械学習、そして総合したデータの視覚化に至るまで、過去と現在の距離が最小まで縮減され、その上で将来を予期して映像としてアウトプットしている。この一連の作業があまりにスピーディであるため、作品タイトルに仄めかされているように、過去と現在の様々なデータが「反復」され「反映」されて、イメージが生成されている仕組みはセンセーショナルであり、まさにメディア・アートの先端であることを実感させるものである。
もう一つの作品は、大脇理智+YCAM《The Other in You》 (2017年)である。こちらもVRを駆使した作品であるが、ライゾマティクスと大きく異なる点は、耳まで隠れるVRのゴーグルを装着してインスタレーションの中央にある球体を両手で触って体験することによる、自由度の制約の部分だろう。その分、作品の体験は没入型に設定されているため、ゴーグルの中に映し出される3Dグラフィックスの映像はクリアでサウンドも鮮明で迫力がある。作品が開始すると、鑑賞者はVR世界内のすぐ近くのダンサーたちの側で踊っているような錯覚を抱き、ダンサーたちがフロアでステップを踏んだりするとその衝撃が球体を通じて両手に伝わってくる。やがて鑑賞者の視点は幽体離脱のように宙に浮き、自らの身体のアバターやダンサーたちを俯瞰する位置に移動してゆく。

大脇理智+YCAM《The Other in You》 (2017) ©︎YCAM
作品の体験的には、以上の二作品のように、リアルタイムなデータ解析をアウトプットする手法や、VRと没入型ガジェットと合わせたハイブリッドな表現方法との差異として整理しておくことは容易である。だが、両者とも「身体」をモチーフにしていることに何か手がかりがありそうだ。
ところで、決して今に始まったことではないが、メディア・アートに先行するポップ・アートやビデオ・アートでは、エディションとして複製可能な作品のオリジナリティと価値を巡る議論が繰り返され、よく知られるように「アウラ」という一回性を指し示す儀礼的な権威を充てがうことで、アート作品のオリジナリティの尊厳が守られてきた。
メディア・アートの現在においてもさほど変化はなく、ソフトウェアやコードのファイルそして動画ファイルとして存在するメディア・アートも多い中、本来アート作品が保持していて唯物的なものに生じるフェティッシュな交換価値は、極めて判断が難しいものとなっている。したがってメディア・アートは、市販ソフトウェアやオープン・ソースの商業性あるいはツールとしての日用品との差別化を行わなければならない。何しろ、一度こうしたファイルの作品が美術館やギャラリーという制度の外に出てしまえば、本質は違えども、作品は市場で一般的に使われている近似したアプリやプログラムとの違い保証することが難しくなってくるからだ。それゆえに、メディア・アートにこそ、モダニストにつきまとっていたアーティストの手作業の痕跡や造形性がもう一度、頭をもたげてくるのだと思えてくる。
メディア・アートはその弱みを反転させ、「いま・ここ」性を重視し、体験型、リアルタイム、既存環境のハッキング、革新的な研究発表とも呼べるメソッドでオリジナリティを担保してきたのかもしれない。それゆえに、ライゾマティクスは天才的なエンジニアやプログラマの能力を駆使して他には真似のできない複雑な機制を生み出しているし、大脇理智+YCAMの作品は総勢20人を超えるスタッフと研究機関の予算に支えられた大掛かりな装置の展示というところに落ち着いているということも想像はしやすい。
一般的な状況を重ねるとすれば、今日、アートを鑑賞しに美術館を訪れる鑑賞者は、公式サイトやリリース情報で事前に見所をチェックするだけでなく、実際に訪れた際のリア充的な体験をインスタグラムやブログなどへ発信するネタを求めている。そして制度側は、こうして発言権を持った来場者から「正しいリアクション」を引き出すことが目下の課題となっている。半ばウェブの情報だけでも理解を深化できそうなところを、来場することによって得られるプラスαの要素をさらに求められている。
したがって、鑑賞者は純粋に作品の前に放り出されるのではなく、施設のアメニティの品定めはもちろんのこと、作品の情動的なインタラクティヴ性、制作に関わる意図やコンセプト、マニフェスト、制作過程、そして作品説明といった情報の波に晒され、また、撮影可能作品や場合によっては広報が用意した撮影スポットでお決まりの画像を撮って帰るという一連のプロセスに誘導されている。
それを踏まえて「身体」のモチーフについて考えてみたい。公式HPに掲載されているライゾマティクスの作品解説には、西洋美術史の絵画や彫刻を総じて通底する理想的な人体像の描写と、再現性の高い写真など記録メディアが事物をキャプチャし身振りや動きの理解を深めてきたことが述べられている。
大脇理智+YCAMの作品説明には、VR、3D映像、立体サウンドを駆使して、ステージと鑑賞者の慣例的な視聴体験に新たな可能性を提案する狙いが述べられている。通常であれば単なるシアトリカルな関係性が、パフォーマーとオーディエンスがイコールになる状態を発生させ、主客の境界線が揺らぐような瞬間を見出そうという試みであるから、コマーシャルな利用方法もいくらでも想像ができる装置である。つまり研究機関としてはビジネス化も視野に入れることができるというわけだ。
なぜ「身体」なのか。一つは、身体を基礎とするフィジカルな領域は、発展するテクノロジーやサービスによって補完・拡張され、利便性を与えられ、総合的に個々の暮らしを良くするためのものであるというアジェンダが少なからず至上命題として君臨しているからだろう。これはまさしく、メディア・アートに用いられているテクノロジーやプログラミングなど先進技術がいずれ市場に応用されてゆくだろうという未来志向が、現在進行中のメディア・アート表現に亡霊のようにつきまとう、制度の問題である。
現に、私たちを取り巻く消費物やアミューズメントには、ますます五感を拡張した体験方法が求められ、よりインタラクティヴになっている。ベクトルとしては、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚へと進むにつれて難易度が上がってゆくわけであるから、今日、視覚・聴覚から進んで触覚(ハプティック)が研究成果として表れはじめていることは理解しやすい。
ところで、ロシア・アヴァンギャルドやバウハウスなどモダニストたちの例を挙げれば、こうしたアートによる美的判断能力は、「労働」や資本を司る身体と親和性のあるものであり、旧世界を一新し社会秩序を保つための必要不可欠なプログラムであった。
モダニストのなかでも最リベラルな一人とも言えるヨーゼフ・ボイスはソーシャル・アートの概念を提唱した際、誰もがアーティストとして各々の人的資本を活用して社会の格差を無くしてゆくという理想を掲げていた。そういう意味では、ライゾマティクスが鑑賞者の身体的特徴や動きのデータを収集し素材として活用するということには、抽象的な身体の集合としての可能性にかける一つの手がかりを見出すことができるだろう。そして彼らの作品説明には、身体の理想的な美しさの追求というものが、古来よりの美術界のディスクールであり、社会の運営と表裏一体の性格を持つということも連想させてくれる重要な一節が含まれていたはずだ。
しかし、ヨーゼフ・ボイスは重大なポイントを見落としていた。美的能力やクリエイティビティというものには、タレントという単語がうまく言い得ているように、個人差がある。こうした能力は自然が与えてくれる個別的なギフトであるし、資格や教育というものは、環境要因が大きく左右してくる。そして性格にも個人差がある以上、たとえ個人が能力を発揮するにしても、ボイスには、怠惰や消極性といった性質の解決策を見出すことはできなかった。
繰り返しになるが、メディア・アートには、市販物との差別化や制度的な諸条件により、モダニズム的な造形性が、より意識される。
ライゾマティクスの作品において、二点だけ違和感を覚えるものがあるとすれば、それはダンスカンパニーELEVENPLAYのダンスデータの援用と、鑑賞者から収集した抽象的なデータの将来的な使用許諾を求める注意書きである。端的に述べるとするならば、ライゾマティクスは、作品が作品としてスタンド・アローンな美的体験を提供するために、個別の鑑賞者自身には興味を示さず、そして信頼していない。それは、ボイスが解決できなかった鑑賞者の消極性にも似た感覚で、作品が「造形的」に弱くなってしまうからだ。そのため、ライゾマティクスはプロのダンスカンパニーELEVENPLAYのデータを、消極的な鑑賞者の動きとリミックスして美的体験を水増ししている。

Rhizomatiks Research x ELEVENPLAY 《discrete figures》(2018) ©︎NTT ICC
次に、鑑賞者から集められたデータの使用については、下記のように注意書きがされている。「本作品では、お客様の体験の様子を記録し、そこから身体のモーション・データ(動きに関するデータ)、ボーンデータ(骨格に関するデータ)、デプス・データ(深度に関するデータ)、カラー・データ(色に関するデータ)、ムービー・データを取得します。これらのデータはライゾマティクスまたはライゾマティクスが許諾する第三者により利用される可能性がございます。」
ここで個別の鑑賞者は、単なる抽象化された身体とそのフィジカルなデータとしてしか認知されていない。そもそも固有名も肖像も容姿の特徴も剥ぎ取られた生データなのだから、個別に誰のものかをアイデンティファイすることはほぼ不可能なのだが、ここではそういったデータがまるで個人情報のごとく用心深く扱われている。この収集によって大人数のデータを集めることができれば、将来の作品が造形的にそしてコンセプト的にそれなりの強度を持ちうるという制作側の思惑は想像することができる。
大脇理智+YCAMによる《The Other in You》についても同様である。パフォーマーとオーディエンス間のシアトリカルな関係に一石を投じるような身振りではあるが、映像自体は始まりと終わりのあるリニアな物語作品であるし、鑑賞者のアバターは単なる傍観者であって、周りで「タレント」を備えたダンサーたちがプロの腕前を披露するものだ。つまり、主客の根本的なスタンスには変わりがない。
本作は、むしろこれからより顕著になるであろうメディア・アートに触れる参加者側の個人の能力差の扱い方についての状況をシニカルに風刺する作品としては見所があるかもしれない。というのも、本作はインタラクティヴなエンタテインメントが求められている市場に敏感に反応すべく、商業的に応用可能なテクノロジーの発表としての狙いが感じられるものの、「ダンス」のフォーマットを採用したことで、以上の身体的差異や、ダンスをする・できる能力というタレントの不平等さを浮き彫りにする批評性が、むしろ明るみに出ていると言えるからだ。
3.ポスト・ヒストリカル、そしてポスト・ヒューマンへ (Post-History and/or Post-Human)
さて、もはや鑑賞者はミシェル・フーコーが掲げたヒューマン・キャピタル(人的資産)の細分化したタレントに分断されてしまった向きさえある。ヒューマン・キャピタルを主軸とした資本主義の姿を見出していたフーコーは、いずれ生産者自らが消費者となり、そして再び消費者が生産者になるというループの出現を予期していた。現に、消費者目線という言葉が商品開発やマーケティングで日常的に多用されている事実は疑いようがない。
同様に、アートは本来のアート作品の物神的交換価値とは異なる商品化(Commodification)の波に晒されており、アーティストはアート・マーケットの要求や公共のテイストに合うようなコミッション制作や作品の提示を迫られて、アート自体の信頼性が崩れつつある。それゆえに、アーティストたちが逆にこうした公衆を分析し、抽象化し、素材に変えてしまうことは何らおかしなことではない。
このアブストラクションを究極まで突き詰めると、もはやアートの展示価値や作品価値、公共の欲望といったリニアな人的要因にまみれたディスクールを超越したところで、ポスト・ヒストリカルな作品が現れてくる。一つは、東京大学池上高志研究室による「Artificial Life Larger than Biological Life」である。本作については、HPの解説や展覧会場のアーティスト・ステートメントをいくら眺めてみても難解すぎて考察が極めて難しいのだが、Artificial Life(人工生命)の研究を専門とする池上研究室では、AIの基礎となる知能や意識というものはそもそも生命の副産物であるのだから、その生命の原初的な発生のしくみを、数学的なアングルで、例えば膨大なデータの中に現象する生命的な振る舞いなどに見出そうとしている。

池上高志研究室「Artificial Life Larger than Biological Life」 筆者撮影

池上高志研究室「Artificial Life Larger than Biological Life」 筆者撮影
ただし、こうした数学的な人工生命研究のヴィジュアライゼーションは極めて抽象的でアンビエントであるため、鑑賞者は手がかりのない、雲をも掴むような感覚に襲われる。すなわち、池上をはじめとする研究室のメンバーたちが頭に描く複雑な数式と視覚的な言語は、はじめに日本語や英語といった全く趣の異なる言語に置き換えられるため、ほとんどオリジナルの直接的な文脈やメッセージが伝達できていないのではないだろうか。
だがまさに、これこそが鑑賞者や人間を超越した、ポスト・ヒストリカルな作品の姿とも言うことができそうだ。モダニズムではフォルムが内容に対して優位に立っていた。内容とは、まさに鑑賞者を主体としたアートにおけるポピュリズムにとっての最大の商品である。筆者の読解力の無さと言われればそれまでであるが、池上研究所の数学的なヴォキャブラリーの、コミュニケーション言語やヴィジュアル言語への翻訳が破綻しているという状態は、逆説的にオリジナルの数学的実体の形而上のフォルムの優位性を物語っているのである。
だがアートとして破綻しているのではない。なぜなら、マクルーハンが描き出したメディウムとメッセージの関係—-つまりアーティストの表現の成功にとってまず大前提であるのが、伝えたいメッセージを、それが自ら意図する方法で視覚的に伝達できるようなメディウムと合致すること—-を念頭に置けば、池上による数学的な人工生命の「発生の」研究がマッシヴ・データ・フローの中に生命的な動きを探るという作業自体がすでに私たちの歴史観から乖離しており、ポスト・ヒューマンなものであるという明白なメッセージがしっかりと表現されているからである。
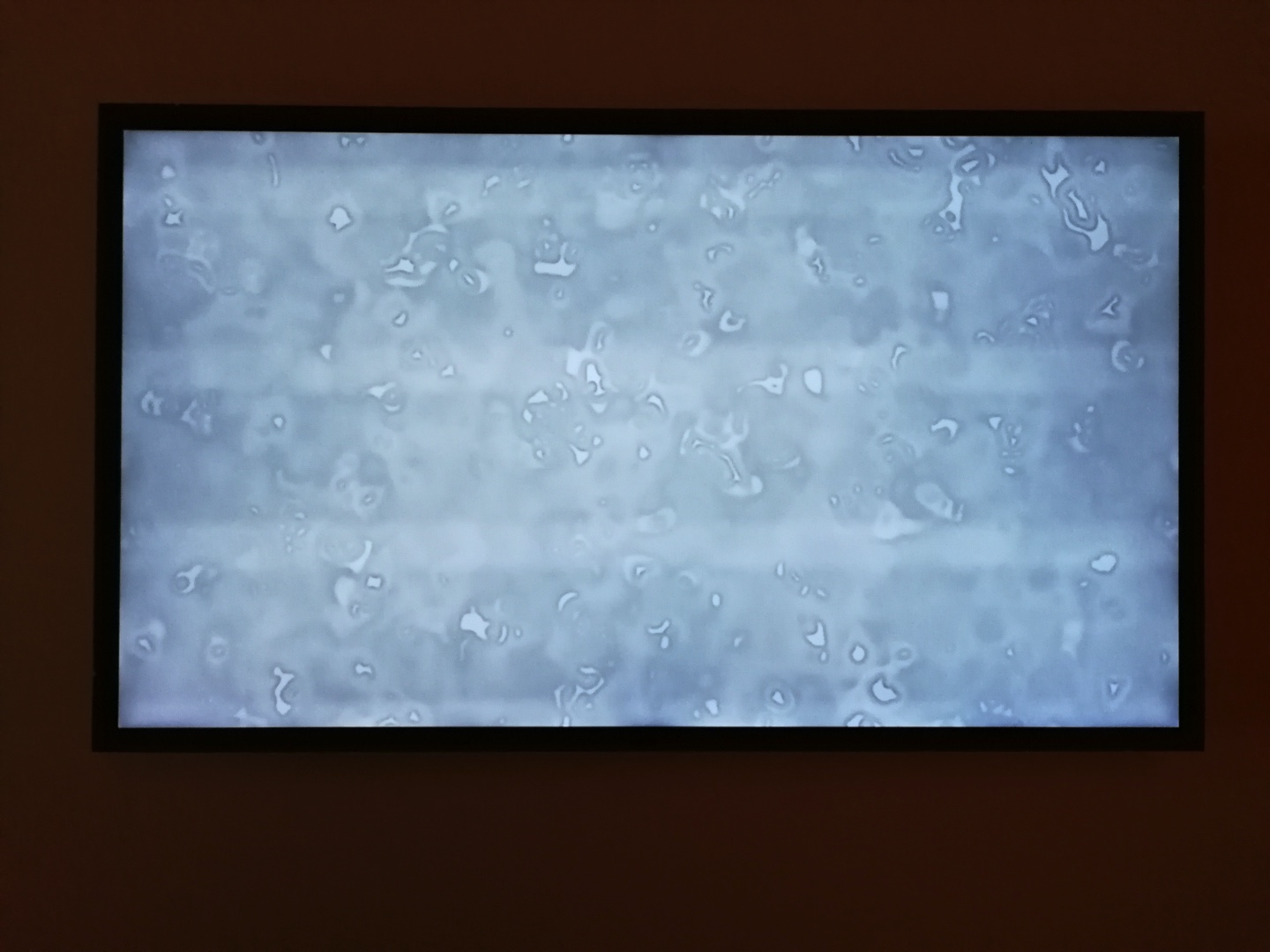
池上高志研究室「Artificial Life Larger than Biological Life」 筆者撮影
そしてもう一つの作品が、宇治野宗輝《ライヴズ・イン・ジャパン》(2018年)である。壁に無造作に掛けられた大小6台のモニタは、家電やカスタマイズされた楽器などガジェットの群を映像として映し出している。するとそれぞれの装置はスイッチが入り動き出し、複数の装置が同期して鳴り出したり、オーケストラのようにシンクロしたりする。本作のように、回路やプログラムによってレトロな機械や装置に音を出させるというところは、一見、伝統的なメディア・アートさながらだ。実際、アーティストは大量消費や大量廃棄社会という言葉を用いて風刺的なスタンスも匂わせている。

宇治野宗輝《ライヴズ・イン・ジャパン》(2018)©︎UJINO, courtesy of Yamamoto Gendai / 撮影:木奥恵三
注目したいのは、アーティストがこうして様々な装置を組み合わせた作品を物理的なインスタレーションではなく、あえて映像のフォーマットで発表しているということだ。アーティストはその意味するところを、物質から情報へといった社会の移り変わりとしている。確かにそれは読み取れる。すでに人間のいない世界にあって、物質から単なる情報へと実体を失った装置たちが叫んでいるのだ。同時に本作は、アート作品特有のフェティッシュな価値の生まれてしまう状況について考えさせる契機を提供している。
ここでアート作品の物質性と、同様の物質性に生まれる物神的価値について触れておこう。アートは、機能や用途を持たないため、アートである。ハイデガーによる、アート作品が真理を開くという例に詳しいように、ゴッホが描いた、くたびれて使い古された『農婦の靴』は、人間の目を介すると視覚的な用途が見えてきて、農婦の暮らしや農作業の厳しさなどのナラティヴへの地平を開くものであるが、作品自体は、靴を描いただけの絵画であるゆえに使用価値すら見出せない単なる物質ということになる。だが、そこには内容に関わらず、ラディカルな交換価値が生じる。マルクスはこうした交換価値が使用価値を上回る現象を呪物崇拝(Commodity Fetishism)と呼んだが、アートは、道具でもない、単なる物質でもないという意味で、反対にそれらの真実を暴き出してくれるのだ。

©︎President and Fellows of Harvard College
話を《ライヴズ・イン・ジャパン》に戻してみよう。仮に装置が実際の物質を組み合わせたインスタレーション作品であったとしよう。それぞれの装置はツールとしての目的や用途があるのだから、道具ということになるが、カスタマイズされ総合してアート作品となる場合、こうした道具たちはアート作品の物質性に直接的に回収され、それら自体が単体では想像もつかない交換価値を得ることになる。しかし本作は、こうした装置たちの動きを撮影してモニタで映したものである。すると、ゴッホの絵と同様に、撮影された道具たちはいくらまとまったとしても物質性には回収されず、アート作品の表象を形成する実体のないデータということになる。そこで浮き彫りにされるのが、何の変哲もないモニタの道具性と、それが不気味にもアート作品の交換価値に極めて近づいてくる物質性である。一体、映像データに価値があるのか、それともモニタに価値があるのかという、アートの存立そのものの呪物崇拝に関わる問いかけが、ここで展開されているのである。
さて、筆者が「イン・トランジション」で感じた環境的・制度的な移行の流れをまとめてみるとすると、前者はGoogle、Appleそして自動運転技術など広く普及した情報ツールやシステムを所与の環境とみなすポスト・インターネット・アートの現在的表現が、いかに私たちが身近なテクノロジーと反省的に渡り合ってゆくかの手がかりを示していたかということが一つ。
そして、制度的な移行という切り口では、VRや3D映像のシステムに焦点を当て、モーション・キャプチャなどによる鑑賞者のデータ収集を人間の抽象化と捉えながら、その行為が消費者目線のアミューズメント化あるいは商品化してゆくアートの潮流に対する批評的なスタンスの一種であると述べた。そして、もう一つの制度の移行の考察では、人工生命の研究における数学的言語と視覚メディアの不一致を逆説的に意図されたものだと捉えながら、すでに作品の対象が人間の歴史観から遠ざかっていること、そして人の姿を挟まない道具やガジェット重視の映像作品が、ポスト・ヒストリカルなあり方で、物・道具・アートの存在論的位相のあり方を多様的に示してくれたことを考えてみた。
最後になるが、以上の難しい話は抜きにして、現在のメディア・アートは映像や装置のクオリティが高くて単純に楽しめる。言い方は悪いかもしれないが、エンタテインメントとして受け入れたとしても、五感に訴え夢のような特別な体験をさせてくれるものであることは疑いを挟む余地はないだろう。だからこそ、ICCで展開されている反省的なメッセージや研究開発の発表を含むバラエティに富んだ作品群は、現在の私たちを取り巻くテクノロジーやツールをうまく使いこなすためのヒントであると思えるし、近い将来への予備知識を身につけるきっかけにもなってくれるだろう。
「オープン・スペース 2018 イン・トランジション」は2019年3月10日(日)まで初台のICCインターコミュニケーションセンターにて開催中。
※James Bridle, “New Dark Age” (2018)